
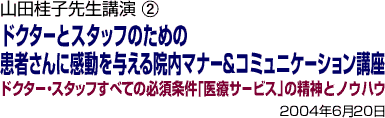

アポイントシステム=藪医者?!
さて、昭和38年、山梨県の甲府というところで開業いたしまして、患者さんがおいでになる状況というのは「先生、ここ痛いから診て」と、どんどん入ってくるような状況なのです。そうすると「少々お待ち下さいませ。午後の2時からいかがでしょうか」「なんだ、診てくれないの。じゃあいい」患者さんみんな素通りです。たまに私が一生懸命「あなたのご都合に合わせてよい時間をちゃんとお取りしておきますから」というとおいでになるのです。
当時は煮沸消毒です。ゴボゴボ炊いて、ようやく熱いのをおろして、2時においでになる患者さんをお待ちしていると、いらっしゃいました。「あ、患者さんおみえだ」と思うと、それをそっと出してはさみでつまんでようやくセットする。そして待合室に行ってみると患者さんはいなくなっているのです。そこで私はお宅に電話をかけてききます。「お待ちしているのですけれども」「お宅いや、気持ち悪い。誰も待っていないんだもの」という具合で、「藪医者」というレッテルがそこではられて、大変苦労いたしました。
今はほとんどの医院がアポイントメントシステムだと思うのです。ただ私には、患者さんとの関係がいったいどうなっているかというのが大変心配です。というのは、ほとんどの患者さんが受付をのぞいて「空いている、空いている、じゃここ」みたいな。「私都合悪い」電話かけてくる。だめになる。外で衛生士さんに「私、約束があったけどだめなのよ。また次にする」などという非常に安易なシステムにされてしまった。簡単にキャンセルもできるし、席もバスの順番をとるようだというのがどうも私は気がかりです。アポイントメントシステムとは、全く違うコンセプト、そこには厳然たる医療と患者さんによる契約事項があるのです。
定期検診の先導
そんなふうなことを、ちょっと古いお話から私どもが乗り越えてきた苦労を垣間見ていただきたいと思います。
その次からもっといろいろなことが起こりました。「一口腔一単位」の診療というチャレンジがあって術後定期検診を打ち出しましたら「やっぱりあいつは変り者、自分の患者さんの定期検診してどうなるんだろうな」それはそうです。前に治療した歯をふたたび定期診療したら、悪い診療していたらまた何かしなくてはいけないのです。ですから先生方に「ばかだな」なんていわれたり、とにかく日々プロブレム&ハプニングでした。今ここに衛生士さんが大勢いらっしゃいますが、今患者さんは歯みがきに対して、みんなにこにこして「もうちょっと教えてちょうだい」なんて非常に積極的ですけれども、昔は大変でした。
コーディネーターとしての役割
 ほとんどの患者さんが私の前をプンプン怒って通りぬけます。「どうしたんですか?」「子どもじゃあるまいし、何言ってるんだ。おれは一人前の男なのに歯ブラシをこうしろなんて衛生士が言った。なまいきだ」怒ってみんな帰ってしまうのです。私はある時とうとうたまりかねて、院長の気持ちを考えて患者さんを別室に通して、歯をみがくということは実はこういうことなのですという説明を始めたのがきっかけで、私は耳をダンボのように大きくして、目を最大限開いて、良く見て良く聞いて、私は患者さんとこの医療というものを柔らかく結びつける役、コーディネーターとして自分の存在を確保いたしました。ですから私はとても忙しかったのです。
ほとんどの患者さんが私の前をプンプン怒って通りぬけます。「どうしたんですか?」「子どもじゃあるまいし、何言ってるんだ。おれは一人前の男なのに歯ブラシをこうしろなんて衛生士が言った。なまいきだ」怒ってみんな帰ってしまうのです。私はある時とうとうたまりかねて、院長の気持ちを考えて患者さんを別室に通して、歯をみがくということは実はこういうことなのですという説明を始めたのがきっかけで、私は耳をダンボのように大きくして、目を最大限開いて、良く見て良く聞いて、私は患者さんとこの医療というものを柔らかく結びつける役、コーディネーターとして自分の存在を確保いたしました。ですから私はとても忙しかったのです。
患者さんをひとりひとり大切に扱うのがプライベートデンティストリーです。パブリックデンティストリー、即ち保険医療医は大勢いらっしゃいますが、プライベートデンティストというのは少ないものですから患者さんの疑問や質問がいろいろあります。そこで私どものところでは、患者さんが入り口に立たれたときから、そのことがわかるようにプレゼンテーションしているのです。
プライベートデンティストリー
それはどういうことかといいますと、私どもの医院のコンセプトは、あらゆるところに見えることになっているのです。たとえば百人診る当時有名だった先生は、長いすに患者さんがみんなもたれあうように、嫌ですよね、暑いときはくっついて。でも長いすに座っている。これではプライベートじゃないのです。プライベートじゃないところに座らせてプライベートに扱おうなんて、どだい無理なのです。
もともとプライベートデンティストリーというのは、アメリカ人のように非常に自分というもの、個人というものを自分自身が大切にし、また他人を大切にしようとするそういった宗教からくる生活みたいなものからでておりますから、本当にすべてが違うのです。ですから私どもは非常に努力いたしました。
でも今の時代、先日も自由診療と保険診療が一緒に請求できるようなシステムに変革するようなきざしを、新聞で拝見しました。私はここにお集まりの先生方、それからハイジニストの方、受付の方、それからアソシエトの方、アシスタントの方、みんなこれから患者さんを尊重して個人として扱っていくことによって、患者さんの要求がだんだん高くなって「先生、インプラントはおできになりますか」などと、患者さんの方から質問される、そういうふうな時代になってくると思います。
そうなると先生方もいろんな勉強をなさならくてはならない。わけてもコミュニケーションの勉強は相当先に進んでしておかなければならない時代がきていると思います。
「歯科医療」というステージに立って
私、大変手前勝手で、自分の医院をモデルにしてお話しを進めがちなのですが、私はちょっと考え方が違っております。実は私は舞台生活が何年かあります。そこでプロは本物でないと誰も認めてくれないということを身を持って学びました。そういう意味で私が考えますのは、皆様方は「歯科医療」というステージに立ったお一人お一人がスターだということなのです。
まず一番大切なのはコンセプト。院長先生がお持ちになっているコンセプト。私は、先日も眼科医院の従業員研修にまいりましたけれども、「先生、コンセプトは何ですか」とお聞きしましたら「患者さんに光を」目の悪い方ですから「光」をというのがコンセプトだとおっしゃいました。ところが、入り口は転ぶような階段で、「光」というその思いがどこに表現されているのか、誠に不思議でした。看護婦さんたちは患者さんに、とてつもない大きな声でお話をなさいます。その時私は「目のみえない方は心で聞くことができるくらいの耳をお持ちなのに、なんであんな大きな声で話すのかしら」と思いました。
院長先生は舞台のコンセプトを作る。そして皆様はそれぞれのプロフェッショナルでありながら、そのコンセプトに向かって踊り、歌い、話す、そういうタレンテットなのです。そういう意味で私はこの医療をステージだと思っています。何故ならば患者さんは、自分をどう扱ってくれるかを注意深く客観的にみている。そして何を隠そう、愛というものを探していると思います。とくに今の世の中、愛が足りなくなっているというか、私は愛というのは人間の中にある能力であると信じていますから、愛を出す機会がない、それから出てもそれを認めてあげない、それでお互いの愛というものが交流できない、そういう感じがいたします。そんなことで、私の話の中にはスター性みたいなものとか、あるいはこの自分の思いを形にして相手に表して伝えようとするさまざまな行為、表情、そういったものの説明やそれから実際に皆様方にしていただく、スターとしてやっていただくような場面がたくさん出てくると思います。
<< 前ページへ |
次ページへ >> |